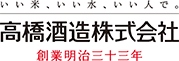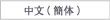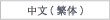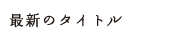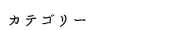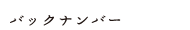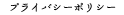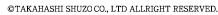第162回 少女漫画は突然に
2018.05.01
私が結婚について真剣に考えるようになったのは30歳に手が届くような年齢を迎えてからのこと。
それまではお気楽に趣味の世界で生きてきたけれど、ある日突然このままではいけないと考えるようになった。いずれ私も高齢者になる時が来る。そのとき一人でいたら話し相手もなく淋しい思いをするのではないか。
だが私は交際している男性もない。もちろん、これまで交際したこともない。男とつきあうなんて面倒と思っていた。そうも言ってはいられないということなのだ。
どうやれば結婚相手の男性と知り合えるのか。
ネットの出会い系も嫌だった。事件に関わるニュースをよく目にしていたし。もちろん街で気に入った男性に声をかけるなんて、はしたないし。私は容貌は劣っていないと思うけど。
「ちゃんとした結婚相談所に紹介してもらうのがいいわよ」と同い年で主婦をしている友人が言った。その言葉に従う。しかし、どんな結婚相談所へ行けばいいのかしら。
さまざまな紹介所の案内を比較していて、目に留まったのがここだ。
「あなたの人生の記念すべき場面を忘れられないものに!ベスト・パートナーのことはおまかせー当紹介所には"出会い演出一級設計士"が在籍しています」
出会い演出一級設計士......そんな資格は聞いたことがない。しかし、そこに惹かれた。
訪ねるとシステムと料金の説明を受けた。高いのか安いのかわからない。「どんな風に出会い演出を設計されるのですか?」
「それは、あなたのデータを分析してからです。お一人づつ内容はちがいます」と質問表を渡された。膨大な数の質問項目だった。
年収に始まり、好みのタイプ、趣味、食べもの、動物など諸々の好き嫌い。スポーツ。まだまだ質問は続く。どこの紹介所もこうなの?
「特にお好きな趣味は少女漫画ですか?」
「は、はい。いけませんか?」
「いえ、大丈夫です。それではときどき連絡をとらせていただきます。一番相性のいい素敵な人と知り合えますよ。あ、でも会費と紹介料の払込をお忘れにならないように」
すぐに振り込んで、しばらく経つが何の連絡もない。私はいつもどおりの生活を続けた。
ひょっとして、騙されたのだろうか?
そして連絡があった。紹介所の出会い演出一級設計士の男からだった。
「これから申し上げることを守ってください。いつもより15分遅れで出勤してください。ただし口にパンを咥えて」
「えー。会社に間に合いませんよ」
電話は切れた。私は仕方なく紹介所の言葉に従って出勤した。口にはパンを咥えて。
駆け足の出勤だった。「遅刻!遅刻!」
バス停近くの曲がり角で衝撃が。
尻餅をつくと、前でスーツ姿のイケメンも尻餅をついている。ぶつかったのだ。
私はかっとなって叫んだ。「何よ。ぼーっとして。会社に遅れちゃうわ」
すると向こうの男も「君の方こそ不注意だろう。あんなスピードじゃ、出合い頭にぶつかるじゃないか」
「何よ!」
「何だ」
「こんなことしてたら遅刻だわ」
と、その場はそれで別れてしまったが、思い出せば、なかなかハンサムな男性だったような気がする。でも、私に謝りもしないなんて許せないわ。
しかし、心の隅で、何か引っかかるものを感じていた。ひょっとして......これは出会いの演出では......?どこかであの場面は知っている気がする。
その日の午後、例の結婚相談所から連絡があった。
「次の守っていただきたいことです。こんな日は、図書館へ行って好きな本を借りてください。ぜひ。きっと、いいことがありますよ」
私は、その言葉を信じて近くの図書館に、その日の帰り道に寄った。
ふっ、とある予感がよぎったが、その考えをすぐに振り払った。そんなことが計算でできるものか、と。
そんな私の好きな少女マンガのような出来事が。考えてみれば、出合い頭にパンを咥えた主人公がイケメンとぶつかる少女マンガがどれだけあったことか。
そして、その日の図書館で、私は読みたかった「クロノス・ジョウンターの伝説」を借りることにした。梶尾真治の名作だ。こんな機会でないと読めないから。
探し続ける。そして、やっと見つけて指を伸ばす。すると同時に誰かの手がその本に触れた。
慌てて顔を上げると、向こうも私を見る。同時に一緒に声を上げた。
「あーっ。あなたは今朝私にぶつかった人!」
こんな偶然が起こる確率はどのくらいなのだろう。
おずおずとお互い言葉をかわすと、なかなか感じのいい人だということがわかった。それからどちらから誘うというわけでもなく、彼と私は付き合うことになった。
なんと彼の趣味も少女マンガを読むこと。
そして、例の紹介所に照会した。「この出会いは計算されていたのですか?」「それは企業秘密ということで。でも結果的によろしかったのなら、それでいいのでは」と答えが返ってきた。
私たちは結婚した。彼にあの紹介所を利用したのか聞こうかとも思うが、聞かないままだ。いい出会いの思い出だから、知らなくてもいい気もするし。
そして、私たちは子どもを授かり、今では成長して小学生だ。なるほど少女マンガ好きの二人に生まれた子だな、と思うのは、娘がバレエを習いたいといい出したことだ。まさに少女マンガらしい出来事は子にまで引き継がれるのか。今日、娘が言った。「私のトゥシューズに誰かが押しピンを入れていたのよ」
これも、どこかで聞いたような。