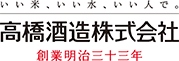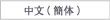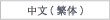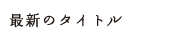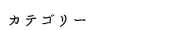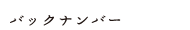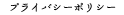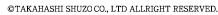第163回 完璧な殺し屋
2018.06.01
私には、どうしても殺したい男がいる。理由やら、そいつがどんな人物かということはどうでもいいだろう。話してもいい。話せばなるほどと納得してもらえるはずだ。だから理由は省く。ただ、そいつを殺しても世の中の誰も悲しまないし困らない。むしろ喜ぶ。
しかし、どんな人物でも殺せば私は捕まってしまう。殺し屋を雇っても、殺し屋が捕まり依頼した私の名を出せば身も蓋もない。
だから、私は完全犯罪をやる必要がある。
完全犯罪。
私が絶対に捕まることがない殺人。
しかし、古今のミステリーを読む限り、完全犯罪は成立しないようだ。さまざまなトリックを用いても、不可能アリバイを考えても、名推理をする探偵や刑事が謎を暴いている。
では、どうすればそいつを殺すことができるのだろうか?そいつを完全犯罪で殺す方法が見つかるのなら金に糸目はつけないのだが。
殺害方法に思いを巡らせつつも良い案を思いつかずに、一人で場末のバーで飲んでいたときのことだった。
カウンターの隣りにいた男たちの会話が、自然と耳に入ってきた。
「いやぁ、あんな医者がいるとは驚きだよ。わかっていたら父を絶対連れて行かなかったのに」
「もっと早く知っていれば絶対に止めたのに。うちの町内で、あの医者に何人殺されたと思う?」
「そんなに凄い医者だったのか!まるで、連続殺人犯だなぁ」
二人は喪服姿だった。父親の葬儀明けに友人と来たようだ。私は思わず二人の会話に割って入った。
「今、連続殺人...と仰言っていましたが誰のことですか?」
二人は申し訳なさそうに首を横に振る。「酒の上で口を滑らせただけです。気にしないでください」
「いえ、ぜひ聞かせてください」
仕方ないという表情で一人が口を開いた。
「私の父がかかった医者の話ですよ。その医者がとんでもない藪でして。咳が少し出るというので診せると容態がみるみる悪化して、あっという間に亡くなってしまったんですよ。今でも信じられなくらいです」
すると、もう一人が話を続けた。「とにかく医者という名の災厄です。彼の手にかかると患者は、どんな軽い病でも死に至るほどの藪ですよ。彼の病院の門をくぐる者は、全ての望みを捨てろ!と言われているほどです」
「ほほう」私はかすかな希望を持った。
もしやこれは。
「医者としての腕は最悪です。ところが会ってみるとこれほど人当たりの良い好々爺はいません。まるで宗教家のような神々しさを備えた藪医者です。本人は善意で誠心誠意治療にあたるだけに質が悪い。その結果は......。人間性は非の打ち所がないのだが。無類の酒好きという点を除いては」
酒に目がないのは私も似たようなものだ。
「知らずにうちの町内の者たちがその医者にかかったけど、全員が数日で病状を悪化させて病死しました。致死率百パーセント」
これだ!と閃いた。この医者を殺したい男のところに送り込めば、これこそ完全犯罪ではないか。医者は必死に治療にあたるが、一生懸命になるほど標的は死に近づいていく。しかも医者本人に殺意は皆無なのだ。それどころか、その医者は善意の塊という。
「その医者のところに行ってみたい。どこの医者ですか?」
二人は顔を見合わせ迷ったようだが渋々教えてくれた。私が患者になるわけではないから、手土産に大好きだという酒を持って病院に向かった。
すぐに、その病院は見つかった。確かに訪れる患者もいないのだろう。入り口にクモの巣が張っている。看護婦の姿もないし。中に入ると人の良さそうな白衣のおじさんが現れた。
まさに善人。殺意のかけらもない。
「おや、具合がよろしくないのかな?」
「いえ、お願いがあってきました。これは手土産です」と酒を出すと大喜び。本当に酒好きらしい。
「他に患者もいないし、お上がりください」と診察室へ。コップに酒をつぎ飲み始め、私にも「付き合ってくださいよ」とコップ酒を渡す。言われるままに一杯だけ付き合うことにした。
「どんな用件ですかね?」
「世間で評判を耳にしてうかがいました。名医だそうですね」本人は嬉しそうにうなずく。自分ではそう思い込んでいるらしい。
「訪問診療とかやっていただけますか?医療費は私が出しますが」
「もちろん。今は仕事が暇だから、丁寧に診療するし、すぐに治療に入りますよ。ご指定の場所までうかがいます」
しめた!と喜んだ。
「ただ、医学にも限界がある。必死で治療しても功を奏さないことがあることも覚悟して欲しい」と弁解めいたことを言う。自分の藪っぷりに罪の意識はあるらしい。これは本物だぞ。嬉しさのあまりコップ酒をゴクリと飲む。そして「こちらの方の診療と治療をお願いしたいのですが」とメモにペンを走らせようとしたら、手が痺れて書けない。それどころか胸が...胸が「苦しい~」
すると、医者はしまった、という表情に。
「かなりお疲れの様子とお見受けしたので、さっきのお酒に元気回復剤を混ぜて進ぜたのだが。副作用が出たようじゃな。あ...これは、いかん。特製の気付け薬を注射してやろう!」
なんと殺傷力の強い藪っぷりか。
完全犯罪の計画は完璧だったのに...。
やめろ!注射しないでくれ!助けてくれ!そう叫ぼうとするのだが、悲しいことに私の意識は遠ざかっていくのだった。