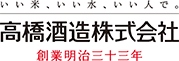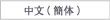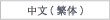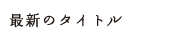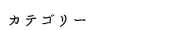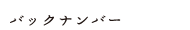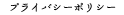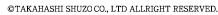第167回 鬼童岳の霧女
2018.10.01
九州脊梁の北東部にある鬼童岳に登ったときのこと。鬼童岳は、まずなだらかな草原から杣道へと入る。しばらくダラダラ登り続けると、足元はガレ場へと突然に変わる。それから胸を突くような急斜面となり、それが八合目の山小屋の手前まで続くことになる。少し登れば右へと曲がり、そのまま山道を進むと今度は左に折れる。ひたすら荒い息を吐きながら一歩づつ足を動かしていくしかない。
その日は生憎の天気だった。
登山口に着いたときに、曇っているなとは思ったものの何とか行けるのではないか、と判断して歩き始めた。ポツリ......。すぐに頬に冷たいものがあたる。大降りにならない予感があったので、登山道の脇でリュックから雨具を取り出して急いで身につける。
人気のある山ではないので、私以外に登山者の姿はないようだった。
あたりを急速に霧が覆い始める。濃いミルクの中にいるようで、数十センチ先は何も見えない。かろうじて、足元の石くれを見て、進む方向を判断するしかない。石段を一歩づつ登っていく。しばらく前進すると、右へ曲がる場所に。そこでU字型に曲がる。一人で登っているから、足を進めることだけに神経を集中させて、他のことまで気が回らなかった。
しまった。スタート時間を覚えておくべきだった。どこまで登っているのか見当だけでもつけられたのに。
ゆっくりと登る。それから方向を変える。ジグザグというたどり方をしているのだろう。どこまで来ているのか?半分ほど登ったろうか?心細い気持ちになった。
孤独の山歩きとはこんなものだ、と自分に言い聞かせる。真っ白い風景の中で立ち止まり、ペットボトルの水を飲んだ。
そのとき気配を感じた。人だ。他にも私同様登山者がいて登ってきているのだ。
少しほっとして、その場に立ち尽くした。声がする。若い女性の声だ。笑い声があがる。どんな人だろう。
「やだぁ、本当ですか?」
「そうよ。でも山歩きって楽しいでしょ」
明るい声にほっとした。どんな関係の女性たちなのだろう。
「人生って、山登りに似てると思わない。ほら今日みたいに。周りを見ても真っ白で、何をしてたか、どんなところにいるのかもわからない。でも、できることといったら、前にひたすら進むしかないのよね。これって人生そのものじゃない」
「先輩、かっこいい!」
そうか。職場の先輩、後輩という関係か。先輩は山好きみたいだな。そして二人が霧の中から姿を現す。あんなかっこいい科白が吐けるなんて、どんな女性だろう?
「こんにちは」と私が言うと、二人も立ち止まり「こんにちは」と会釈を返してきた。二人とも若くて美人だ。
「あっ。せっかくだから先輩、お願いしましょう。先輩と二人の記念写真を」「いいですよ」と私は答えて若い子のカメラを受け取り、二人に向かって「はい、チーズ」と声をかけながらシャッターを押した。私に礼を言った二人は「もうすぐ山小屋よ」と再び登り始める。しばらくの休息の後、私も登り始めた。引き返そうか迷ったが、彼女たちに元気をもらったようだ。この小雨だ。また八合目小屋で彼女たちも休憩するだろう。私も山小屋まではがんばろう。
八合目小屋の手前で雨がひどくなった。途中、他の登山者に合うことはなかった。小屋の戸を開けると声がした。「戸は閉めてください」男の声だ。ここで食事にしょう。座ってお茶を飲み、おにぎりを食べた。管理人の男が、掃除を終え「おつかれさまでした」と声をかけてきた。山小屋は彼だけのようだ。世間話をしながら話は途中で会った二人の女性のことになった。そして言った。「かっこいいことを言うんですよ。人生は山歩きに似ているなんてね」管理人の男は大きく目を見開いた。「出ましたか」「え?」「霧女って呼んでます。登山道が霧に包まれると、その女たちが出るんですよ。別に悪さをするわけじゃない。ただ、ひょっとして私が知っている女たちの誰かなのかもしれないって、いつも思いますよ。私もよく言ってたんです。女の子を山に連れて行くとき。霧の日の山歩きって、人生に似ている。今まで何をどう歩いてきたか、振り向いても見えないけれど、前に足を踏み出すしかないって。その女たち、誰なんでしょう。いや、人からは聞くけど私は会ったことがない」若い女性たちは霧女という幽霊ということなのか?
結局、山小屋に若い女性たちは姿を見せなかった。
私はもう山頂を目指す気もなく、小屋を出て一目散に登山口を下り始めた。もちろん、途中誰一人会うこともなかった。足元に注意しながら登山口に戻ると、雨具を着た老人が一人、登山用の杖を補充しに来ているのが見えた。鬼童岳森林を守る会の腕章をしていた。「おや、こんな日に登られましたか?」「ええ、若い女性たちも登っていました。霧女だったそうですが」と私は苦笑した。老人は不思議そうに首を傾げた。「若い女性立ち......。見かけませんなあ」「いや山小屋の管理人さんから聞いたのですが」すると老人は信じられないようすで眉をひそめた。「山小屋は閉鎖されていますよ。中に入れない筈です。管理人は恋人とその友人をあの山小屋で殺して、自分も自殺したんですよ。以来、あの山小屋は閉じたままになっている筈です」ぞくっとして私は自分の車に戻ろうとした。しかし「本当に山小屋にいたんです」と振り返ると、老人の姿はかき消え、どこにもなかった。老人が持っていた杖が登山口に転がっているだけだった。