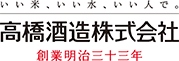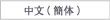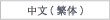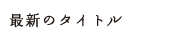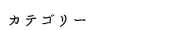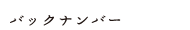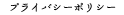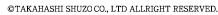第176回 盂蘭盆の子
2019.07.01
先祖の霊を敬い祀る行事が盆だ。盆には亡くなった家族が戻ってきて数日を過ごすのだと言い伝えられている。盆は新暦で迎える地方と、旧暦の七月十五日前後にやる地方とがある。私の本家は、七月の盂蘭盆(うらぼん)だ。子供の頃からどもその時期になると私は両親とともに本家を訪ね、数日を過ごした。他の親族たちも集まり、夜は宴会となった記憶がある。十三日の宴が始まる前には玄関先で迎え火を焚き祖先の霊を迎えた。この三日間は父は休みをとり本家でゆったりと過ごした。毎日宴会が続き、それは十五日の夜の送り火まで続いた。父の兄妹たちも家族連れで集っていたので、本家は祭りのような賑やかさだった。
それが盂蘭盆に関する私の思い出だ。私は昼間は従兄弟たちと一緒にセミやカブトムシを探しに山に出かけたり、川へ鮒をすくいに行ったものだ。だから、本家に集まる全員を見知っていたはずなのだが。
思い出すと、どうしても引っ掛かることがあった。
謎の女の子のことだ。
初めて気がついたのは小学生になって初めての盂蘭盆のとき。それ以前にも実家の盂蘭盆には行っていたのだが気がつかなかっただけなのかもしれない。
玄関先に皆が集まっていた夕暮れ。迎え火を焚くために叔父の一人がマッチを擦ろうとしていた。私はその横にしゃがみこみ、点火されるのを待っている。
二つ歳上の従兄弟も腕組みをしてしゃがみこんでいた。その隣に、その子がいた。
女の子だった。やっと歩けるようになったくらいの子だった。見知らぬ子だった。どこの子だろう。今までどうして気がつかなかったのだろう。あとで迎え火が終わったら確認してみなければ。そして、迎え火が終わり、家の中に入る。そのとき、あの女の子の姿はどこにもなかったのだ。私は女の子のことは誰にも尋ねなかった。ひょっとしたら自分の目の錯覚だったのではないかと思ったから。
翌年、同じように親戚一同が盂蘭盆のとき本家へ集った。そして同じように迎え火を焚こうというとき。
その女の子は現れた。一年経っているから、私は背が伸びていた。しかし現れた謎の女の子はよちよち歩きのまま、全く成長していなかった。一年前と同じ水玉の服と短パン姿のまま。一番背が伸びる時期なのに。女の子は私を見ていた。そして私と目が合うと嬉しそうに微笑んだのだ。私も思わず微笑みを返していた。女の子が誰なのか知りもしないのに。女の子が目の錯覚などではないことを確信できたからでもあったろう。だが、迎え火が終わり皆が家の中に戻ると、その年も嘘のようにその女の子の姿は消えていた。その年、母親に尋ねてみた。
「やっと歩けるくらいの女の子いたよね。どこに行ったの?」と。
母親は不思議そうだった。「そんな小さな女の子は、いないよ。何か勘違いしているのかね」ショックだった。私は実在しない女の子を見ていたのだ。それから、私は迎え火を焚くときに会う女の子のことは、口にしなくなった。しかし、翌年も、その翌年も女の子は出現した。私を見るといつも笑いかけてきて。思わず私も笑顔を返したものだ。
その次の年の迎え火の前に思いついたことことがあった。迎え火とは亡くなった家族を迎える行事ではないか。女の子が生者であるとは限らない。迎え火の前にすでに帰ってきている祖先の一人ではないのか?
私は、祖父に尋ねてみた。「この家で生まれてすぐ亡くなった子って今までいなかったの?おじいちゃんの妹とか」
祖父は不思議そうだった。それから、よく考えて答えてくれた。「おじいちゃんの代まで考えてみたが、幼い頃亡くなった子どものことなど聞いたことないよ。何故だね?」理由について、私は答えなかった。
その年の迎え火のときに、初めて女の子は現れなかった。
小学校を卒業すると、盂蘭盆に本家を訪れる習慣もなくなった。
高校へ進み、大学へ行くために親元を離れた。大学を出ると故郷の会社を選び入った。やはり、育った土地で暮らすのが落ち着く。
七月に入ると、ふと子どもの頃迎え火のときに見た、幼い女の子のことを思い出した。いったいあれは誰だったのか。
勤めで知り合った女性と私は結婚した。もう立派な社会人だ。親はずっと私が結婚しないのではないか、と心配していたようだ。決まった女性と交際するような縁がなかったからだ。だが、妻とは仕事先で出会ってから嘘のようにとんとん拍子で話が進んだのだ。結婚して、挨拶に妻を本家に連れて行ったときのことだった。「ここに来たことあるわ」と本家の玄関前で妻は言った。「家で遊んでいたとき、気がつくといつもこの場所にいた。皆で火を焚いていた」まさか......あのときの女の子は......!「目の前にいた子が誰かはわからないけれど、あなたに会ったとき懐かしい気がして」彼女が初めて笑いかけた表情に惹かれた理由が私にはそのとき、はっきりとわかっていた。「そうよ。みるみる成長していなくなったけど、笑顔の素敵なあの男の子はあなただったのね!」