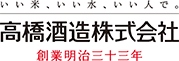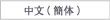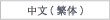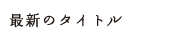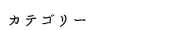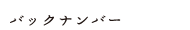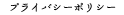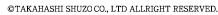第39回「クロノス・ジョウンターの伝説クロニクル」
2008.02.01
クロノス・ジョウンターというのは、私なりに考えた不完全なタイムマシンのことです。
過去の目的の時間へ搭乗者を跳ばすはずなのですが、過去に滞在できる時間が限られていて、一定時間を経過すると過去から弾き飛ばされてしまいます。それも、出発した時間ではなく、未来へ跳ばされてしまうのです。
この第一作(吹原和彦の軌跡)を「グリフォン」という雑誌に書いたときは、クロノス・ジョウンターを使った話をこれからも書こうなぞ、考えもしませんでした。
すると、編集さんが「クロノスで一冊、本にしようと思うんです。でもこの一篇だけでは本になりませんから書き下ろしをお願いしますよ」
そうか。クロノス・ジョウンターだけで一冊の本になるのもいいなぁ。そう考えて、安易に「いいですよ」と引き受けました。前回の作品は、切ないがハッピー・エンドの話とは言いづらいなぁ、と考えていたので、「愛は時を超える」というコンセプトだけ共通で、ハッピー・エンドの話(布川輝良の軌跡)を書いて、めでたく一冊になったのです。
それが一九九四年のこと。
時が流れます。一九九八年になり、クロノス・ジョウンターのことなんかすっかり忘れていた私のところに、またしても編集さんから電話が。
「今度、クロノスを文庫にしようと思うんですよ。けっこうクロノス・ファンが多いんですよ」
「ああ、嬉しいですね」
「で、文庫にしてページが薄くなるんです。ここで、もう一篇、書き下ろしを入れると、ファンは喜びます。売れ行きも違います。ぜひお願いします」
「でも、もうアイデアありませんよ」
「いや、大丈夫です。梶尾さんなら、アイデアは湧いてきますから」
「そ、そうですか?」
私は褒めに弱い人間なのです。「じゃあ」と口を滑らせたばかりに第三作(鈴谷樹里の軌跡)を書く破目になりました。
編集さんは、その言質をとった翌日からターミネーター編集さんに変わりました。
ひいひい呻きながらアイデアを捻り、やっと完成しました。原稿を渡すとき、編集さんに言い添えました。
「もうこれが最後です。もう叩いても押しても頭は空っぽです。クロノスは、もう書けません」
すると編集さんは不気味な科白を残して電話を切りました。「いゃあ、クロノスは進化する話ですから」
それから、月日は流れ、クロノス・ジョウンターを原作とする「この胸いっぱいの愛を」が映画となり、演劇集団キャラメルボックスで「クロノス」というタイトルで舞台化もされました。二〇〇五年のこと。
この舞台化に便乗しようとしたのでしょう。またしてもターミネーター編集さんは、私に連絡をとってきたのです。
「で、そろそろクロノスの新作を書いて頂いて、タイムトラベル作品集を出そうと思うのですが」
「もうクロノス・ジョウンターの話は思いつきません」
「そこを何とか。時間ものなら何か出てくるでしょう」
食い下がってきます。「二、三日考えさせて下さい」その場しのぎの答えをして電話を切りました。確実にターミネーター編集さんは、T—1000編集さんになっていました。三日後、債権の取り立て屋のように電話が。
「いかがでしょう。アイデアの方は」
「あの。クロノス・ジョウンター方式は浮かびません」
「じゃ、他の方式ではいかがですか?」
「か・考えてみます」
それで考えたのが時間は螺旋状であるという理論。
書きました。それが、「君がいた時間ぼくのいく時間」です。
嬉しいことに、この作品も演劇集団キャラメルボックスで二月から舞台化されることになりました。しかも主演はイメージしていた上川隆也さんがやることに。
楽しみだなぁ、とぼんやり考えていたら、またしても、T—1000編集さんから鬼のような電話が。
「せっかくの舞台化です。クロノスを新書で出しましょう。そして目玉は、新作の書き下ろし」
あんぐりと口を開き返事もできません。もう、ネタがないと、さんざん言い続けてきたのを知っている筈‥‥。
「まだ、過去へ跳んでいない人がいます。野方耕市とか」
この編集さんはT—1000どころではない。地獄で亡者を苦しめる獄卒の化身です。
野方耕市はシリーズに必ず登場するクロノスの開発者です。
書きました。そして、もうすぐ発売です。
「クロノス・ジョウンターの伝説∞インフィニティ」(朝日新聞社)「野方耕市の軌跡」に加えて、短編「栗塚哲夫の軌跡」も。
ええ。血を吐く思いで書きましたとも。
「やっと、クロノス・ジョウンターの伝説が完結しました。もう書けません」
原稿を渡す際に、そう言い添えました。十四年にわたってのシリーズかぁ、と感慨もひとしおです。
獄卒編集さんが、空々しい相槌しか打ってくれなかったのが不安です。
それから「クロノスはインフィニティですから」と。