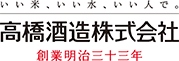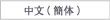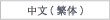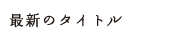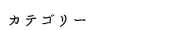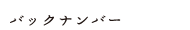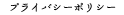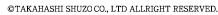第5回「球磨拳」
2006.06.08
「頼もー!頼もー!」
ぼろをまとい、長い髪をした眼光の鋭い若者が門前で大きく叫ぶ。背は巨人ほども高く、胸の筋肉は、ぼろ着からはみ出んほどだ。握りしめた拳ゆえか、腕の隆々とした筋肉からミミズのように血管が浮き出ていた。
「何じゃろう。大きな声で叫びなさるは」
白く長い顎髭をはやした小柄な痩せた老人が屋敷の奧からひょっこひょっこと姿を現した。
若者は思った。
(ム、この老人。できるな。ただ者の身のこなしではない)
無意識に背筋を伸ばし、胆田に力を込めた。それから深く礼をする。そして若者は言った。
「突然お邪魔して申し訳ございません。私は、全国を拳の奥義を極めんと行脚の旅を続けているケンスローと申すものです。その行き先で、拳の達人と手合せ頂き、腕を磨いております」
「ほほう。どれほどの腕の方かな」
老人は、顎髭をしごきながら尋ねた。
「失礼!では、あの石灯籠を」
ケンスローは、あ・た・た・た・たと甲高い声をあげ両手を繰り出した。その後に石クレが無数に転がっているだけだった。
「いかがでしょう。石灯籠の秘経路を突きました。岩手拳の技でございます。他にも、不乱拳、南斗幽拳も習得いたしております。この人吉盆地を訪れ、貴方様が、古式ゆかしい球磨拳の達人であるとお聞きしました。ぜひ、一手、お手合せをお願い致したく」
老人は呵々と笑い、言った。
「ケンスロー殿は誤解しておられる。球磨拳は、勝負はつけるが、人を殺める拳ではござらん」
「では、どのようにして雌雄を決するのでございますか?」
「うむ。じゃんけんの一種と思うてくれ」
「じゃんけん。ぐーちょきぱーの!知らなかった・・・」
「そうじゃ。だが、ちとルールはちがうぞ。パーよりグーが強いのじゃ。グーは〝彼氏〟に負け、〝彼氏〟は〝鉄砲〟に負ける。〝鉄砲〟は〝お金〟に負けるという具合だ」
「そ・・・それは謎の言葉」
「指じゃ、指の形を示しておる。パーは5。グーは0。〝彼氏〟は親指で1。〝鉄砲〟は親指と人差し指で2。〝お金〟は3。そして四本指で4。一つづつ多い数を示した方が勝ちということだな」
ケンスローは、ぽかんと口を開けた。身のこなしは素早いが、頭の回転はあまり速くなさそうだ。
「まあ、勝負するのは、無理のようだな」
立ち尽くすケンスローに、老人は、そう声をかけた。
「お待ち下さい。せっかくはるばる訪ねました。そのルールで球磨拳のお手合わせをお願い申しあげます」
老人は、頭を振りながら、仕方ないのぅと拳を握った。
「では、やるか。ひい・ふう・さんで出すのじゃぞ」
「はい」
「では、ひいふう・さん」
ケンスローは、習い性だろうか。両掌で、あ・たた・た・た・たと拳を繰り出した。
「ほれ、ほれ、ほれ、ほれ、ほれ。すべてわしの勝ちじゃな」
老人の手はすべてパー。4の指を出し続けたケンスローに勝っている。
「な、何故、私の手が読めたんですか?」
ケンスローが愕然と叫んだ。
「簡単じゃよ。四本指で無意識のうちに秘経路突きを出しておったからな。さあ、飲みなされ。球磨拳のルールだ。負けた分、焼酎の杯を乾かさねばならぬ」
「な、なんと」
「焼酎は白岳の〈しろ〉だ。味には問題なかろうて」
杯を重ねるケンスローは見る見る真っ赤になっていった。
「まだ飲ませるのですか?」
「それほど連続して負けたということじゃ」
ケンスローは、すでに満足に立てない状態だ。しかし、懸命に挑んでくる。
「先生、もう一手、球磨拳を」
老人はニヤリと笑って言った。
「おまえの負けじゃ。おまえはすでに酔っておる」
「何!」
愕然とケンスローは膝をついた。
ケンスローが酔拳に開眼するのは、それから三年後のことであった。