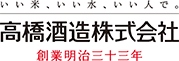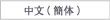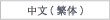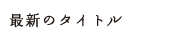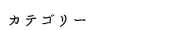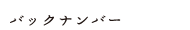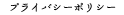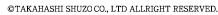第2回「チョック・ストーン」
2006.05.30
「市房山に一緒に登ろうよ」
そう言い出したのは、妻だった。
ゲッと思う。最近、妻が登山にこっているのは知っていた。しかし、私まで巻き込まれるとは思ってもいなかった。苦しい思いをして、山道を登って、何が楽しいのだ。
「お願い。今度の結婚記念日に。装備は私が揃えるから」と行った。「山歩きに一度だけつきあって!」
「厭だよ。身体がもたないよ」
「ゆっくり登ればいいの。あなたのペースに合わせるわ。無理だったら次からは誘わないから」
市房山に登ることになった。まさか、妻は私が知らないうちに、私に生命保険をかけたのではないだろうな。おもわず疑う。だが、その気配はないようだ。
結婚記念日。私たちは、湯山温泉に泊り、早朝、市房キャンプ場近くの登山口をスタートした。この日のために、妻は登山靴を買ってくれた。安いものではないはずだ。私が二度と山に登らないと言ったら、この登山靴は靴棚ふさぎと化すだろう。勿体ない。だが、それは口にしない。市房神社に着く前に、すでに私の息は、フイゴと化した。心臓の鼓動は早鐘のようだ。私はへたばったふりをする。妻は、諦めてくれるかと思いきや、私の回復を辛抱強く待っていた。これでは歩き続ける以外にない。頂上には、一般登山者であれば三時間半で到達すると妻は話していた。
「その倍の時間かかってもいいのよ」
登りが延々と続く。ひたすら歩く。
「いい景色でしょう」周囲の風景など見えない。視野が狭くなっている。
「空気がおいしいわ」空気を味わう余裕などない。喘ぐだけだ。
二〇分ほど登り、休み、また登る。
「もういやだ。歩かない」岩場にへたりこみ、妻の反応を見た。妻は、黙って腰を下ろし、私を見ている。回復を待っている。「もう、ここは九合目よ」励ますようにぽつりと言う。
また歩く。ひたすら登る。少し、苦痛が消えてきたようだ。巨木や巨石が眼に入るようになった。頂上に着いたのは登山口から四時間半後だった。もう登らなくていいと思うと放心状態になった。標高一七二二メートルよく登ったと自分に呆れた。四方に下界が見渡せる。
「すごいわ、あなた。ちゃんと登れたのね」
妻が誉める。悪い気はしない。妻はカメラを出した。「記念撮影してあげる」
「ああ、いいよ」と応じたが、妻は、首を横に振った。「ここより、もっといい撮影ポイントがあるの」
もう少し、頂上の先にあるという。その場所に連れていかれた。「あの岩の上に乗って」
カメラを持つ妻に言われるまま、その岩の上に立つ。下を見て驚いた。私の立った岩は中に浮いたような状態になっている。チョック・ストーンというやつだ。
妻が言った。
「その岩は心見の橋というの。病ましい心の持主とか嘘つきは、そこから落ちちゃうって」
それから、私がどう反応するかを待っているようだ。私は高所恐怖症であることが自分で初めてそのとき自覚した。そして、妻が私をここ迄連れてきたがった理由を知った。
「ああ、そうなのか。さぁ、早く写してくれ」妻はうなづき、カメラを持って言った。
「私のこと、今も愛してる?」
バカ!と言いたかった。妻はシャッターを押さずじっと、待っていた。仕方ない。
「あたりまえだろ」と答えた。まだシャッターを押さない。
「ちゃんと言って」私は言った。顔から火を吹く思いで。妻は続けた。
「今まで、浮気したことある?」
「ない」叫んだ。めまいがした。シャッターが押された。私は、そんな言い伝えは、信用しない。そのくらい、平気で答える。私は、心見の橋から落ちることはなかった。
しかし、女はいくつになっても幼稚さが消えないと私は思う。妻は来年が喜寿、私が傘寿になろうというのに。帰り道、妻は笑顔だった。
だが、こう付け加えた。
「あなた、あそこで嘘ついて落ちなかった人は、死んだら地獄に落るって知ってますか?」
私は「知らない」と答え、溜息をついた。